対立と紛争が続く現実の状況下でも、
それをコメディにできる人間の底力。
Content
映画 「テルアビブ・オン・ファイア」 世界も心も燻ぶり続ける
脚本:ダン・クラインマン、サメフ・ゾアビ
監督:サメフ・ゾアビ
日本公開:2019年
〈Story〉
エルサレムに暮らすパレスチナ人のサラームは、叔父バッサムがプロデューサーを務めているアラブの連続ドラマの制作現場で働いている。
ドラマのタイトルは、『テルアビブ・オン・ファイア』。1960年代の第3次中東戦争前夜を舞台に、女スパイのマナルが、イスラエル軍の将軍イェフダと、テロリストの恋人マルワンとの間で揺れ動く大人気ドラマ。
ドラマではヘブライ語が使われているため、ヘブライ語を話せるサラームが、発音指導として脚本に携わっている。撮影中、サラームは脚本家に、イェフダがマナルへ語るセリフ『君は爆発的だ』の変更を要求した。
爆発的というのは女性への侮辱的発言だと感じることから、「美しくて気絶しそう」というサラームの代案が採用される。
その日の仕事帰り、サラームは撮影所から自宅に帰る時に毎日通るイスラエルの検問所の人に、「女性に対して爆発的というのは褒め言葉?侮辱?」と尋ねる。
爆発物を持っていると勘違いされたサラームは車から降ろされ、検問所の主任アッシ・ツール司令官の元へ連れてかれる。アッシはサラームが、妻が大好きなドラマの脚本に携わっていると聞き、自分にだけドラマの結末を教えてほしいと頼む。
困ったサラームは、逆にアッシに、どんな結末がいいか尋ねました。
するとアッシは、「マナルはテロリストの恋人マルワンではなく、イェフダと結婚するべきだ」と答えるのだった。。。
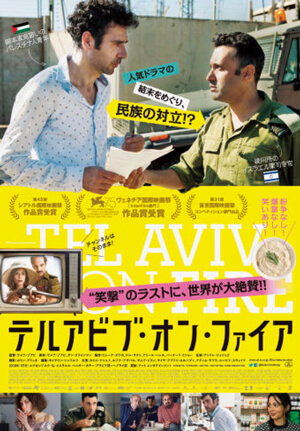
僕が今回選んだのは「テルアビブ・オン・ファイア(2019)」で、タイムリーな作品です。6年前に映画館で観た時はパレスチナ問題をよく知らなかったのでピンとこなかったんですが、改めて勉強してから観ると、ぐいぐい引き込まれました。
ざっくり説明すると、テルアビブはイスラエルの実質的な首都です。本当の首都はエルサレムですが、経済・文化の中心はテルアビブにあります。
紀元前1世紀頃、この地域にはユダヤ人の王国がありましたが、ローマ帝国に滅ぼされ、ユダヤ人は追放されて世界各地に散らばります(ディアスポラ/離散)。
ユダヤ人がこの土地を自分たちの国だと信じるのは、モーゼがユダヤ人をエジプトからカナンの地へ導き、ここを彼らの国とした。(旧約聖書 出エジプト記)
その後、アラブ人がパレスチナ地方に住むようになり、この地域をパレスチナと呼ぶようになりました。
ユダヤ人はヨーロッパで迫害され、第二次世界大戦中のナチスによるホロコーストを経験します。その過酷な歴史を経て、「自分たちの土地さえあればこんな悲劇は防げる」と考えるようになりました。これが「シオニズム」です。19世紀末から第二次大戦終結までに、多くのユダヤ人がパレスチナに戻ります。
映画「栄光への脱出(1961)」の物語ですね。
しかし、そこにはすでにアラブ人が住んでいたため、土地を巡る争いが起こります。これが現代のパレスチナ問題の始まりです。イスラエルにはユダヤ人が住み、パレスチナ自治区にはアラブ人が住むという複雑な状況になっています。エルサレムはユダヤ教・キリスト教・イスラム教の聖地であるため、争いが終わりません。
どうして聖地が集中しているんですかね(信仰が違ってもこの地の同一神を祀るという不思議)
1947年、イギリスが統治していたパレスチナですが、イギリスが匙を投げます。国連のパレスチナ分割決議によりユダヤ人とアラブ人に分割されます。ユダヤ人は自分たちの国ができたことを歓迎しましたが、元から住んでいたアラブ人は猛反発。翌年、イスラエル建国宣言がなされ、周辺のイスラム諸国との間で中東戦争が勃発します。以後、4回の戦争が起き、イスラエルとパレスチナの関係は複雑化しました。
ずっと戦争が続いているね。
1993年、オスロ合意によりパレスチナ自治区が誕生。イスラエルの中にはガザ地区(種子島程度の面積)とヨルダン川西岸地区(三重県程度の面積)の2つの自治区があり、それぞれチェックポイントで管理されています。
ガザ地区はハマスが支配し過激派、ヨルダン川西岸地区はパタ派が支配する穏健派で、統治方針も異なります。ガザでは電気や水道など生活環境が悪く、多くの人が苦しんでいます。最近、ようやく停戦が結ばれましたが、恒久的な解決はまだ見えていません。
ややこしいのが外から調整しようとすると、それが軋轢になる。アメリカが介入するとまた火種になる。
「テルアビブ・オン・ファイア」はヨルダン川西岸地区が舞台です。映画の中で「テルアビブ・オン・ファイア」というタイトルは劇中ドラマの名前で、主人公サラームはその制作スタッフです。ひょろっとした頼りない青年で、パレスチナ人ですが、エルサレムに住み、ヘブライ語とアラビア語のバイリンガル。ドラマ制作ではヘブライ語の指導も兼ねて働いています。通勤には検問所で許可証を見せる必要があります。
タイトルの「テルアビブ・オン・ファイア」は劇中で制作されているドラマ。67年の第3次中東戦争(イスラエルとアラブ諸国国の間で展開された戦争)の前夜が舞台で主人公のパレスチナ人の女性スパイ・マナルが恋人マルワンに命じられて、軍事機密を盗むためにユダヤ人のふりをして、イスラエル軍の将軍イェフダに近づく。恋人マルワンと将軍イェフダとの間でマナルが揺れ動く様を描いている昼メロみたいなドラマです。イスラエル人にもパレスチナ人にも人気があるドラマ。
サラームはドラマの制作スタッフの一人で、お茶くみや小道具の運搬とか雑用係。ひょろっとして頼りない風貌で実はパレスチナ人なんだけど住んでいるところは、パレスチナ自治区外のエルサレムに住んでいる。イスラエルの公用語つまりユダヤ人が話すヘブライ語も話せて、アラビア語も話せるバイリンガル。それが認められてドラマ制作ではヘブライ語の指導も兼ねて働いている。自宅がエルサレムで、ドラマを作っている職場が、ヨルダン川西岸地区の中にあるから通勤には検問所で許可証を見せて通らなければいけない。
ある日、検問所で不審者に間違えられたサラームは、アッシ司令官に「ドラマの脚本を書いている」と嘘をつきます。アッシの家族はドラマの大ファンで、アッシ自身もパレスチナ寄りの内容には不満。後日、アッシがイスラエル寄りに脚本を書き直して渡し、サラームはそれを自分の手柄として提出。結果、脚本家に抜擢されます。
ここのくだりも面白くて、アッシの脚本は、イェフダ将軍がマナルに
「ホロコーストの悲劇を繰り返さないために、俺は軍に入ったんだ。」っていうセリフに、本来の脚本家の人が激怒し、辞退して、その穴埋めにサラームが抜擢される。
その後もサラームは自分のアイディアのように提案してドラマに採用させる。
ラブシーンで、アッシは
「マナルとイェフダ将軍をキスさせろ」って命令するんですよね。イスラム圏内では公然の前でのキスがNGで、ほっぺた同士を合わせるアラブ式のキスに変える。それにアッシは怒って、ひずみが生まれる。
現場からは
「イェフダ将軍をもっと悪人にしろ。子供を殺すとか主人公のマナルを殺すとか」
そこで泣く泣くマナルが癌になる展開にする。その展開にアッシはさらに怒って、ある日、サラームを拉致しちゃう。
「最終話ではマナルとイェフダ将軍を結婚させろ」と。検問所の通行証を取り上げる。
「そういう結末にしない限りはこれを返さないぞ」って脅すのよ。
サラームは通行証がないので自宅に帰れなくて、撮影現場で夜を過ごす。サラームもイスラエルとパレスチナの板挟みになって、悩む様子がこの映画で描かれている。
エルサレムに住んでいる厳しさがあるよね。
監督のサメフ・ゾアビはイスラエル生まれなんやけど、パレスチナ自治区の外に住んでいる。その状況が主人公サラームに反映されている。
デビュー作もパレスチナ人が主人公やったんやけど、2作目を作るにあたって、周りからいろんな人にアドバイスをもらったらしい。最初はありがたく聞いてたんやけど、だんだん疲れてきたんやって。その経験がこの映画に活きてる。
それと、この映画は暴力シーンが一切ない。ヨルダン川西岸地区が実際には半分イスラエルに支配されてる状況なんやけど、軍事的な占領は描かずに「精神的な占領」を描いてる。例えばアッシ司令官が「マナルとイェフダ将軍を結婚させろ」って迫るシーン。監督自身、イスラエルで暮らすなかで、日々感じてた精神的な圧迫をそこに込めてるんやね。
この映画のうまいとこは、サラームが「解決策」を見つけて、一応ドラマを終わらせるんやけど、そのラストは半分投げやりで、結局シーズン2に続きそうな終わり方になってるとこ。まるで「解決のないパレスチナ問題」をそのまま投影したみたいに見える。皮肉っぽいけど、ほんまに上手い構成。
しかも、ドラマの中の三角関係(マナル、恋人マルワン、イェフダ将軍)と、サラーム自身が板挟みになってる状況(イスラエルとパレスチナの間)も重なってるんよね。しかもちゃんとコメディとして笑えるシーンも多い。
ドラマの中のお話と、脚本家としてのお話が並行して描かれるメタ構造の作品。
ドラマの物語と、脚本家としてのサラームの物語が並行して描かれる。さらにサラームにはもう一つ三角関係があって、元カノのマリアムに未練タラタラやし、主演女優のフランス人からも好意を寄せられてる。二人の間で揺れ動く姿も描かれるんやけど、ここがまたユーモラス。
例えば冒頭でサラームが
「俺、脚本家になったんや」って自慢したら、マリアムに
「あなたに脚本なんて書けるわけないでしょ。5分もパソコンの前に座ってられないくせに」って言われる。で、サラームはそのセリフをドラマの中に入れちゃう。イェフダ将軍がマナルを口説くシーンで、同じ言葉を言わせるんやけど、それを見たマリアムが
「えっ、あれは私へのメッセージ?」って勘違いするくだりも面白い。
これはどこの国の製作?
実はイスラエル、ルクセンブルク、フランス、ベルギーの4カ国合作。イスラエルやパレスチナを扱った映画を観るのは初めてやったけど、ガザの軍事侵攻がニュースになったのをきっかけに自分なりに勉強して、この映画を観たら理解できるようになった。
狭い地域やけど、世界の火種ですね。
イスラエルとパレスチナの対立っていう重いテーマを、コメディで描くってすごい。しかも血が流れない平和的な形で。これは外の人間じゃなく、当事者やからこそ作れた映画やと思う。
背景を補足すると、エルサレムって3宗教の聖地やから、国連が「国際都市」として特別な扱いをしてる。だから各国の大使館はテルアビブに置かれてるんやけど、イスラエルは「エルサレムが首都や!」って言い張る。で、数年前にトランプがアメリカ大使館をテルアビブからエルサレムに移した。イスラエルの主張を全面的に後押しする形になったわけやね。
今回のガザとイスラエルの停戦も、バイデン大統領が退任前に功績を残したい思惑があって動いたっていう見方もある。ほんま複雑で難しい問題。
舞台となる場所の説明が難しい。
なじみがないからか、劇中に出てくるフムスって料理も全然イメージできなかったんですよ。昔からパレスチナにある伝統料理で、アッシ司令官がサラームに
「脚本のアイディアを出す代わりにフムスを買ってこい」って言うシーンが何回も出てきます。
ひよこ豆をすりつぶして、練りごま、にんにく、オリーブオイル、レモン汁を加えてペースト状にした食べ物で、パンとか野菜スティックにつけて食べるんです。
ディップやね。
そうそう。ただサラームはパレスチナ人なのにフムスが苦手で、一方でイスラエル人のアッシ司令官は大好物。それも一種の精神的な占領のメタファーみたいになっていて。で、サラームがフムスを嫌う悲しい理由が、最後に明かされるんです。
そういうセンシティブな題材を、当事者がコメディに昇華できるのはすごいですね。
素晴らしいコメント。
俳優たちはコメディアンっぽく演じてるんですか?
いや、全然。オーバーじゃなくて淡々とした演技。特に主人公サラームは表情があまり変わらない。
なるほど。その地域では上映されたんですか?
監督のインタビューでは、イスラエルでも上映されて好評だったそうです。上映禁止にはならなかったって。
サメフ・ゾアビ監督にまたこんな感じの映画を撮ってほしいですね。
あ、そういえば「ワンダーウーマン(2017)」のガル・ガドットもイスラエル出身なんですよね。兵役経験があって、二児の母でもあるんです。あとスピルバーグもユダヤ系です。
あと今回はいろいろ本を読んでいて知ったんですけど、ユダヤ人って血筋で識別するのかと思ってましたけど、人種じゃないんですよね。母親がユダヤ教徒であれば子もユダヤ人とされる。だから肌の色は関係ないんです。
人種ではなく、門徒かな。
そうそう。ただ定義はすごくややこしい。
アブラハムの血脈だったかな。二番目の契約者やね。
イスラエル12部族の祖になるあたりですね。最近、聖書関連の本も読んでみたんですけど、なかなか頭に入らなくて
でも結局、根っこはアダムとイブですよね。
そう。その子供たちが男しかいないのに、どうやって人類が繁栄したんだろうって思うんですよ。
イブはアダムの一部から作られた存在って設定ですもんね。
そうなると、結局一人なのか…って。
そこが女性蔑視の始まりかもしれませんね。
実は「バービー(2023)」もそのモチーフをなぞってるんですよ。イブがマーゴット・ロビー演じるバービーで、アダムがライアン・ゴズリング演じるケン。彼らが人間界に行って、知らなかったことを知ってしまう=禁断の果実を食べる、っていう流れ。すごく似てます。
なるほど。次の世代のカインとアベルの兄弟殺しの話は「エデンの東(1955)」の骨格になりますね。
人類初の殺人ですよね。事情を知らなくても楽しめるけど、元ネタを知ると一層深い。
聖書のモチーフってめっちゃ多いですよね。北欧神話も面白いです。
学生時代にちゃんと勉強しておけばよかったって後悔してます。
やっぱり知識をかじっておくのは大事ですね。映画がもっと面白くなる。ギリシャ神話もね。
親殺しの物語も、ギリシャ神話のオイディプス王が原型ですしね。
Eくん
年間 120本以上を劇場で鑑賞する豪傑。「ジュラシック・ワールド」とポール・バーホーヘン監督「ロボコップ(1987)」で映画に目覚める。期待の若者。
キネ娘さん
卒業論文のために映画の観客について研究したことも。ハートフルな作品からホラーまで守備範囲が広い。グレーテスト・シネマ・ウーマンである。
検分役
映画と映画音楽マニア。所有サントラは2000タイトルまで数えたが、以後更新中。洋画は『ブルーベルベット』(86)を劇場で10回。邦画は『ひとくず』(19)を劇場で80回。好きな映画はとことん追う。
夕暮係
小3の年に「黒ひげ大旋風(1968)」で劇場デビュー。開幕し照明が消えると、大興奮のあまり酸素が不足し気分が悪くなって退場。初鑑賞は、あーなんと約3分でした。映画の黎明期から最新作までの系譜を追求。

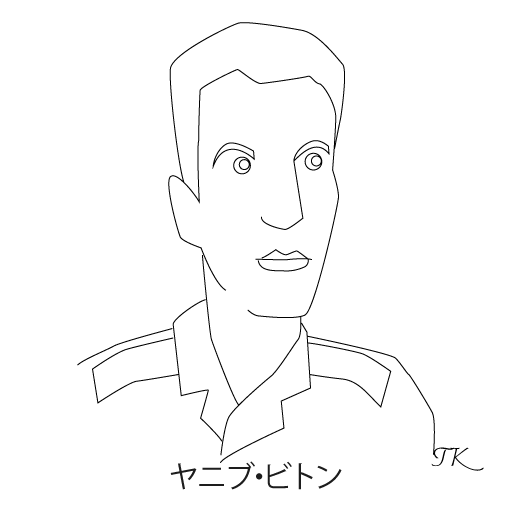
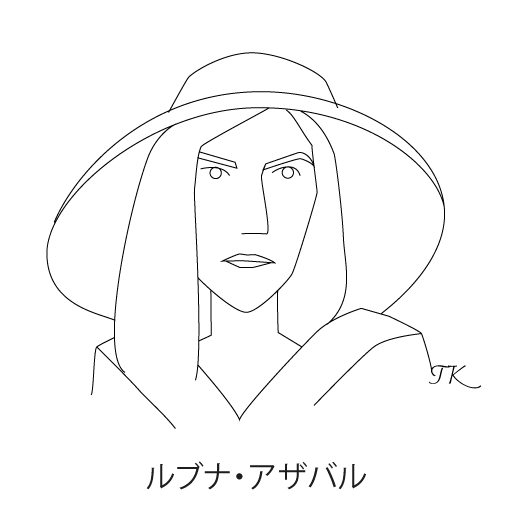
検分役の音楽噺 ♫
今回はアラビア半島に関する映画音楽のことでも書いてみようか、と思いましたが、聖書が関わる映画のタイトルを幾つか挙げていただいているので、そちらのお話を。
僕の家は代々浄土真宗のなので、いわゆるキリスト教の教えを受けたことは無いのですが、映画では昔から聖書を題材とした史劇作品が好きで、特にそこに流れる音楽も壮大かつ映画音楽のスタンダードになっているものも多いです。
旧約聖書を題材とした作品では『天地創造』(66)が有名ですね。
音楽は日本の作曲家、黛敏郎が担当したのも話題になりました。
元々はエンニオ・モリコーネが担当される予定だったのが大人の事情で黛氏が担当されたのでした。
他に旧約聖書画題といえば、『十戒』(56)が有名かと。
音楽はエルマー・バーンスタインが担当。個人的にもバーンスタインの作品ではベストに推したい傑作スコア。
作曲したのがまだ34歳の頃で、『荒野の七人』や『大脱走』を担当する以前の大仕事でした。
他に『サムソンとデリラ』(49)はヴィクター・ヤング、『聖衣』(53)はアルフレッド・ニューマンと映画音楽界の巨匠が音楽を担当しています。
一方、新約聖書を題材とした作品では、なんといっても『ベン・ハー』(59)が有名でしょう。
ロージャ・ミクローシュ(かつてはミクロス・ローザという表記が一般でしたが、最近は改められているケースが多いです)によるスコアは、映画音楽のみならず管弦楽曲のスタンダードにもなっている名曲です。
ロージャ・ミクローシュは旧約聖書を題材とした『ソドムとゴモラ』(62)の音楽も担当しています。
先にも書いたように、これらの映画音楽は壮大であり、キャッチーなメロディ・ラインが特長で、僕自身子供の頃に作品共々触れたことが、映画音楽好きになったきっかけでもあります。
いずれの作品もBlu-ray、DVD、配信等々で観ることができますが、スケールの大きな作品ばかりなので、劇場でリバイバル上映されてほしいですね。
聖書の知識が味わいを増す
- サムソンとデリラ(1952)
- 旧約聖書の「士師記」第13章から第16章に記述されている英雄サムソンの物語
- 聖衣(1953)
- キリストの処刑に関わる出来事をローマ側から描いた作品
- エデンの東(1955)
- 旧約聖書のカインとアベルの物語をモチーフにした現代の物語
- 汚れなき悪戯(1957)
- 「キリストの体と血」を象徴するパンとワインをモチーフとし、無垢な信仰が奇跡を起こす物語
- 十戒(1958)
- 旧約聖書の「出エジプト記」を原作としたスペクタクル映画
- ベン・ハー(1960)
- イエス・キリストの時代を舞台にし、主人公ベン・ハーとキリストの受難の物語が交錯
- ソドムとゴモラ(1963)
- 旧約聖書の「創世記」に記されたソドムとゴモラの堕落と滅亡の物語
- 野のユリ(1964)
- タイトルと内容は新約聖書の『マタイによる福音書』6章28節に由来
- 偉大な生涯の物語(1965)
- イエス・キリストの生涯を描いた史劇
- 天地創造(1966)
- 旧約聖書の『創世記』1章から22章までの創造神話を壮大なスケールで映像化した宗教映画
- ブラザー・サン シスタームーン(1973)
- イタリアの聖人聖フランチェスコの半生
- オーメン(1976)
- 聖書の「ヨハネの黙示録」に登場する「獣の数字」「666」から着想したホラー映画
- インディ・ジョーンズ/レイダース 失われたアーク《聖櫃》(1981)
- 聖書の「契約の箱(アーク《聖櫃》)」をナチスとインディが奪い合うアドベンチャー作品
- エレファントマン(1981)
- ジョンがまだ教わっていないはずの聖書の説を暗唱することでジョンの知能が証明されるシーンがある。
- 炎のランナー(1982)
- 原題の「Chariots of Fire」は、詩人ウィリアム・ブレイクの『ミルトン』からの引用で、この詩は旧約聖書『列王記』のエリヤが炎の戦車に乗って空へ昇る場面がモチーフ
- 最後の誘惑(1985)
- イエス・キリストが十字架に架けられる直前、マグダラのマリアと普通の人間として生きたい「最後の誘惑」に揺れる姿が描かれる。
- セブン(1996)
- 第キリスト教の「七つの大罪」(大食、強欲、怠惰、色欲、傲慢、嫉妬、憤怒)をモチーフにした連続猟奇殺人事件を描いたサイコ・サスペンス映画
- エクソシスト(2000)
- 悪魔祓い(エクソシスム)の儀式を描いたホラー映画
- パッション(2004)
- 新約聖書に基づきイエス・キリストの受難と十字架刑までの最後の12時間を描いた作品
- コンスタンティン(2005)
- 聖書に登場する天使や悪魔、地獄を題材にしたアクションファンタジー映画
- 戦場のアリア(2006)
- 作中で聖書が示唆する「愛」や「赦し」のテーマが、敵対する兵士たちが一時的に友情の契機となる
- リーピング(2007)
- 旧約聖書「出エジプト記」に記載される十の災いが起こるオカルト映画
- 死霊館(2013)
- カトリックの信仰と悪魔祓いの要素が含まれるホラー映画
- ノア 約束の舟(2014)
- 旧約聖書『創世記』に記された「ノアの方舟」の物語
- エクソダス:神と王(2015)
- 旧約聖書の「出エジプト記」を基にした作品
- ハクソ―・リッジ(2017)
- 聖書の十戒の「汝殺すなかれ」を遵守し、戦場に武器を持たず出て行く衛生兵の物語
- ノック 終末の訪問者(2023)
- 新約聖書「ヨハネの黙示録」を基にし、訪問者たちを黙示録の「四騎士」や「7人の天使」に譬えるなど、数多く引用した作品
(対話日:2025年1月23日)