今宵のテーマは「アニメーション 映画」。
背景が輝く新海 タッチ や
シルヴァン・ショメのカリカチュア
それらの筆触は署名となってブランドとなった。
映画 「言の葉の庭」 雨と青葉の アニメータータッチ
監督・脚本:新海誠
公開:2013年
〈Story〉
靴職人を目指す高校生の孝雄は、雨の日の午前には決まって、日本庭園内にある東屋で授業をサボっていた。孝雄は東屋で、チョコレートをつまみにビールを飲む女性雪野に出会う。孝雄は雪野にどこかで会ったことはないかと尋ねるも彼女は否定する。雪野は『万葉集』の短歌 「雷神の 少し響みて さし曇り 雨も降らぬか きみを留めむ」 を言い残して去っていった。
関東が本格的に梅雨入りし、雨の日の午前だけの交流がはじまる。
孝雄は靴職人になる夢を語り、ある理由から味覚障害を患う雪野は孝雄の作る弁当の料理に味を感じ始める。雪野は弁当のお礼に孝雄に「靴作りの本」をプレゼントし、孝雄は雪野のために靴を作ることになる。
夏休みに入り、孝雄は靴の専門学校の学費を稼ぐためバイトを始める。雪野はいつもの東屋で、晴れの日は知らない場所みたいだと思う。
孝雄は学校で雪野が古文の教師だったこと、生徒たちの嫌がらせによって退職に追い込まれたことを知るのだった。。。

新海作品はよく観ていますか?
「君の名は(2016)」と「スズメの戸締り(2022)」くらいかな。
「君の名は」を観た後で、めっちゃ流行っていました。
初期の作品は観ていないのがあるかも。
「秒速5センチメートル(2007)」で新海誠監督を知りました。当時は、リアルな背景描写がすごい作品があると話題になっていました。
初めて観たのが「天気の子(2019)」です。その後、「君の名は」を観て、めっちゃいいなって。食わず嫌いでしたね。
今回の「言の葉の庭(2013)」は最近の作品に比べるとこぢんまりとした世界観で、僕は正直こういう方が好みなんです。
「天気の子」や「すずめ・・・」より前だけど、あの背景の緻密な完成度にびっくりするよね。
川の水面に雨がポツポツ落ちるシーンから始まって、実写かと思うくらい綺麗でした。
木の枝が水面に触れるカットとかね。風景に時間を贅沢に使っています。
綺麗でしたね。10年前の作品なんですね。
背景描写は「君の名は」より圧倒されましたね。物語も40分という短い尺で、見やすかったです。新宿御苑、街並みや学校の教室が描かれていて、新海誠のフィルターを通すと、些細なところでも、輝いて見える光の当て方が特徴的だなって思います。
画面に艶があるよね。
そうそう。
新宿御苑って行ったことないんですけど。ちなみに、大阪にあんな所あります?
大山古墳、別名仁徳天皇古墳の通りを挟んで向かいに大きな公園があって、一部が日本庭園です。大阪市内にも慶沢園があるね。
日本庭園って、お寺の中にあるイメージでした。
日本庭園は山と川と海を小さなエリアの中に写してしまう。お寺の庭もそういう意図で作るね。
都会の中にある別世界。幻想的な世界観でしたね。
喧騒を描いているから、静かなカットが立ち上がっていましたね。外との対比が分かりやすい。
雪野と孝雄の二人だけの世界で、それぞれの事情があって、二人の時間が止まっています。そして、二人は雨の日に出会います。
雪野(古文教師)が男子高校生の孝雄に短歌を言い残して行くのも面白い。
雨になれば、あなたを留められるのに、という歌でしたね。
(雷神(なるかみ)の 少し響(とよ)みて さし曇り 雨もふらぬか 君を留めむ)
後日、孝雄が返歌を引用します。雨の日と言わずとも会えるよ、という歌。
(雷神(なるかみ)の 少し響(とよ)みて ふらずとも 吾は留らむ 妹し留めば)
孝雄は靴職人を目指している。
やがて孝雄が雪野に靴をプレゼントする話になります。雪野の時が止まって動けない状態から歩き出すっていうメタファーがよくできていて面白いな。
雪野の靴が何回かクローズアップされるカットがあって、最初は黒色で次が確かピンクで、その次は白っぽい黄色と、だんだん淡い色になって、最後のクライマックスで二人がマンションの階段で本音を打ちあけるシーンは裸足なんです。そういうところも面白い。
だんだん本音が出てくるグラデーション描写やね。途中では、かかとだけ脱いで靴をぶらぶらさせているしね。
足のサイズを測るシーンが良くないですか?
雪野は椅子の上に上がって東屋の天井に手をついて支えている。
そうそう。孝雄が柔らかそうな足にメジャーを巻く。あれは新海監督のフェティシズムかな。
鉛筆を足に沿わせて輪郭を描いてね。
キネ娘さんはどこが良かった?
私は雪野にフォーカスして観ていました。雪野から見ると未来へ歩き出すポジティブな展開になります。孝雄で見ると、二度と会えない別れかなって。
なるほど、雪野に立ち直る手助けをしたから、置いていかれる。
そうね。そんな気がしました。孝雄がまた会いたいって思っているのがキモやなって。
二人の関係が完璧に断絶したわけじゃなさそうでしたし、手紙でやり取りしています。
そのまま関係が終わることも考えられます。結末を観る人に任せる「女か虎か」パターンかな。そんな気がしますね。
「秒速・・・」がそんな話だとか。すれ違いを予測するんですって。
「言の葉の庭」では、トンビの視点の俯瞰の景色がよく出てくるよね。御苑で会う時も、上から観ると二つの傘が両方から庭園に入ってくる。あれは神の視点のようで、二人の出会いと別れを空から静かに見ています。
雪野が以前付き合っていた彼氏が教師っぽかったですけど劇中には姿を見せていないですよね。
伊藤先生は後ろ姿だけです。家で電話しているカットが出てきただけなので不倫関係かなって思いました。雪野のことをあんまり助けてくれなかったですね。
雪野が苦しかった時は口調だけは優しい。後から出版された小説では伊藤先生の視点になっているらしい。
後半で雪野が嫌がらせを受けていることを孝雄が知って、先輩のところ行って、喧嘩になる。あれはびっくりしました。喧嘩するようなタイプなんだって。普段はおとなしそうな感じが急に激昂したので。
そこで雪野と孝雄が抱えているものの違いが如実に表れているなって。学生は3年で終わるじゃないですか。でも仕事は簡単には逃げることはできない。だから、孝雄の行動は15歳の衝動やって思いました。
後先を考えない。
そうですね。夢も未来もある存在。
雪野のセリフで
「今27歳だけど15歳のときの自分と比べてみてもそんなに賢くなってない」
という言葉が印象的でした。自分も27歳で何も変わってなくて。
それはいくつになってもね。
そう感じます?
感じるよ。周りが成長しているのに自分は中学生から精神的に成長していない。
だから、大丈夫なのか? って自問します。
孝雄の中で本気度を自覚するには、殴られに行くしかないのかな。
確かにそのパッションで、どれだけ雪野に対する思いが本物かが分かってくる。
でも確かに子供。子供扱いされているかどうか、が気になって、
「靴職人になんて、なれると思ってないでしょう?」って雪野に訊く。雪野はそんなこと思ってないのに。
雪野にぶちまけていましたよね。
「先生だと知っていたら自分のことを言わなかった」って、僕はむしろそういう孝雄の方が好きですけどね。
そこで子供っぽさが出るのがいいね。
雪野が魅力的なキャラでした。見るからに悩みを抱えて暗い感じですけど、意外と話してみると表情がコロコロ変わって可愛らしくて、何より朝っぱらからビールを飲んでいるギャップが面白かったです。チョコも持っていましたね。
中盤で、孝雄が雪野のお弁当の卵焼きをつまみ食いして「味が変っている」って言うシーンがあって。あれは雪野が味覚障害だからなんですね。
それが後で伊藤先生との会話で明かされますね。
雪野は依存体質かも。
そうね。だからなかなか立ち直れない。
ネットの受け売りですけど、新海監督作品の他のヒロインと比べても、芯の弱い女性です。
雪野が夏目漱石の「行人」を読んでいました。あれも結局は孤独を突き詰める話です。
そういう人だから、自分のことを知らない人と関わりたかったんだと思います。だから自分のことを話さなかった。
公園だけでしか会わないのも分かりますね。
そうですね。
そこから、ゆっくりと気持ちが動いていく。
思いの外「言の葉の庭」が良かったから、これを機に他の作品も観てみようかな。
この作品だけがしっとりしていて、他の作品のモードと違いますね。
最初に言っていた通り、話のスケールも違っている感じですね。
最近の作品はファンタジー色に染まっている。
そうですよね。
ほんの一瞬でしたけどオムライスの描写がめちゃくちゃ美味しそうでした。ジブリに出てくるご飯は美味しそうってみんな言うけど、新海誠も負けてない。「天気の子」のチャーハンやカップヌードル。
「すずめ・・・」のラーメンね。
神戸の三宮のスナックに居候するところですよね。
新海作品では、何が一番好きですか?
「秒速5センチメートル」のインパクトが強かったです。そこから初期作品を観て、「君の名は」でメジャー化したと感じました。
「言の葉の庭」も「すずめの戸締り」も好き。「すずめ・・・」は前情報なしで観て意外性があって、なるほどって感じました。
終盤の東北シーンであかされますね。子供の頃に書いていた日記帳がめくれて、3月11日にクローズアップされて。。。
映像美は、どれも負けず劣らず素晴らしい。
初期に桜の散る描写をアニメで挑戦しようっていう気概がすごいですね。
僕が観ようって思っている作品が「雲のむこう約束の場所(2004)」。
戦争の影響で日本が南北に分断されているっていう設定。あれは長編デビュー作でした。
それまでにも短編を手がけていた。
「秒速・・・」も三話の小編に分かれています。
オムニバス形式で、それも全く別の話なんですか。
物語は繋がっていますね。
「秒速・・・」の実写版が公開されましたね。「君の名は」もエイブラハム監督がハリウッドで映画化にするとか。
キネ娘さんの言うように、新海誠監督は憧れを作品にしているのかも知れない。
「君の名は」は女性の中で賛否があるよね。
そうですね。いい意味でも悪い意味でも性差を感じやすいような気がする。それがリアルな目線だなって思ったりしますね。
特に「天気の子」は顕著かな。オタクっぽい描写があって、自分はそこが好きなんですけど。「すずめ・・・」はそこら辺が抑えられているなって思いました。
女の子が主人公ですしね。
新海、細田、宮崎、高畑、日本を代表するアニメーターってその4人ぐらいですかね。
「パプリカ(2006)」の 今敏(こんさとし)監督がいます。
元ジブリのスタッフも今活躍しています。
スタジオポノックの米林宏昌監督「屋根裏のラジャー(2023)」とか。
ジブリで「借りぐらしのアリエッティ(2010)」や「思い出のマーニー(2014)」を撮っていました。ポノックで撮った「メアリと魔女の花(2017)」はジブリ風ですよね。
検分役の推しは、原恵一監督だそうです。そして、「国際アニメーションデー」の情報も頂いています。
Eくん
年間 120本以上を劇場で鑑賞する豪傑。「ジュラシック・ワールド」とポール・バーホーヘン監督「ロボコップ(1987)」で映画に目覚める。期待の若者。
キネ娘さん
卒業論文のために映画の観客について研究したことも。ハートフルな作品からホラーまで守備範囲が広い。グレーテスト・シネマ・ウーマンである。
検分役
映画と映画音楽マニア。所有サントラは2000タイトルまで数えたが、以後更新中。洋画は『ブルーベルベット』(86)を劇場で10回。邦画は『ひとくず』(19)を劇場で80回。好きな映画はとことん追う。
夕暮係
小3の年に「黒ひげ大旋風(1968)」で劇場デビュー。開演に照明が消え気分が悪くなり退場。初鑑賞は、あーなんと約3分でした。シネマの黎明期から最新作までの系譜を追求。
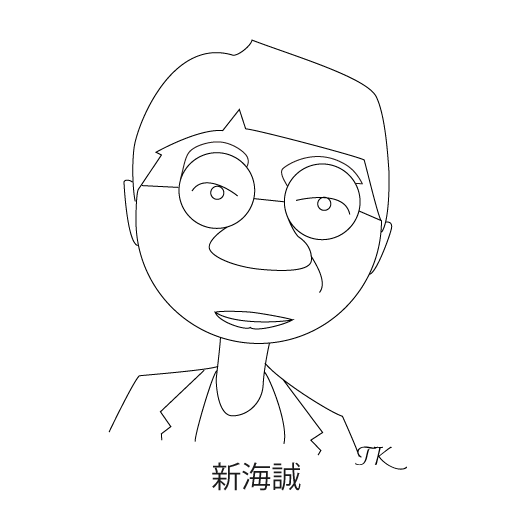
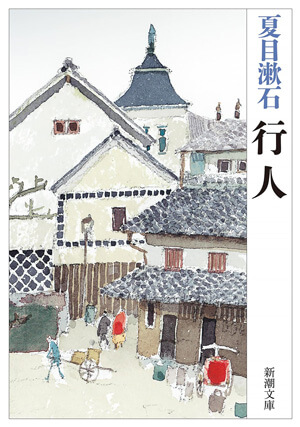
雪野が読んでいた夏目漱石「行人」は、妻に理解されず、両親や親族からも敬遠され、孤独に苦しみながら自分のこころを見つめる、学問だけを生きがいとしている一郎の物語。

フランスのエミール・レイノーが、世界で初めてアニメーションを一般公開した日と言われています。
[イベント]
国際アニメーションデー2025 in 土師ノ里
開催日時:2025/11/15 17:00開場 17:30上映開始
開催場所:Nowherer Hjinosato
国際アニメーションデー2025 in あべの
開催日時:2025/11/22 13:30開場 14:00上映開始
開催場所:四天王寺大学 あべのハルカスサテライトキャンパス
映画 「ベルヴィル・ランデブー」 カリカチュアがブランドに
監督・脚本:シルヴァン・ショメ
日本公開:2004年
〈Story〉
第二次世界大戦後のフランス、孫のシャンピオンを元気づけようと、おばあちゃんはテレビを見せたり、ピアノや犬のブルーノを与えてもシャンピオンの心は晴れない。おばあちゃんはシャンピオンのベッドから自転車の新聞記事がスクラップされたノートを見つける。そこでシャンピオンに三輪車を与えると、彼はそれを乗り回すのだった。
月日が経ち、シャンピオンはツール・ド・フランスへの出場を目指して、おばあちゃんと共に地道なトレーニングを重ねていた。。。

「ベルヴィル・ランデブー(2004)」は、フランスのアニメーションで、20年ぐらい前にシルヴァン・ショメっていう監督が撮った作品です。個人的にはめっちゃ昔から観ていて好きなアニメです。ちっちゃい時から母親が観せてくれて、回を重ねて観ていますけど、未だにそうやったんやって、気づきがあります。
子供の時には分かんなかったこと。
そうですね。記憶の中で変わっていたところが修正されたりとかもあります。今回久々に観ましたね。
一番特徴的なのが新海作品とは違くって、絵本のような感じなんです。人物もカリカチュアされて、ありえない体つきとか目が大きいとか鼻が大きいとか、そういう特徴の絵なんです。
デフォルメ化された感じ。
身長も人によってまちまちです。
鼻が長い人とか。
セリフが無くて、絵で伝えるのが多分主軸にあるのかなっていう作り方をしているんですね。調べて知ったんですけど、「バンドデシネ」っていうのがいわゆるフランス漫画らしいんですけど、シルヴァン・ショメ監督はそこ出身で漫画文化に触れていたそうです。
バンドで、シネって怖いですね。
そんな作品もできそう。
色彩的に落ち着いていて、黄色、茶色、深緑、そんな色合いで統一されています。
全体的に暖色かな。
そうですね。古い紙の色のイメージ。
日焼けしたね。
ストーリーは、おばあちゃんと孫のシャンピオンの二人暮らしなんですね。時代設定が戦後で、その孫の両親は多分亡くなっています。シャンピオンがおとなしい内気な性格で、何にも興味を持っていないので、おばあちゃんがいろんなものをあげて興味を持たせようとするんです。ピアノを弾いてあげるとか、犬を飼ってあげるとか、犬はかわいがるけど、心が輝いていない。
おばあちゃんがシャンピオンのベッドメイクをしている時に、スクラップブックが出てきて、自転車の記事を集めているのを見つけます。自転車をあげると喜んで乗ります。おばあちゃんが読んでいる新聞にはスクラップされた穴が空いています。
シャンピオンが成長して、ツール・ド・フランスに出るんです。その最中にマフィアに誘拐されるんです。それをおばあちゃんが助けに行くのが大きな話の筋です。
その中でも、セリフを言うキャラクターはわずかで、おばあちゃんもほとんど喋りません。どちらかというとこの二人は、表情が表に出ないような描かれ方で家族の中では、犬が一番表情豊かなんですね。
人間はみんな表情がない。
そうですね。 最初の方は、シャンピオンが大きくなると、毎日、自転車の特訓をしていて、雨の日も自転車に乗って坂道を登っている。後ろをおばあちゃんがその昔シャンピオンに与えた三輪車で着いていって、笛吹をピッピッって吹いて応援している。帰ってきたらクタクタで、食卓の上にシャンピオンが寝転んで、おばあちゃんがマッサージをしてあげる。
食事制限もしていてめっちゃくちゃまずそうなご飯が出てくるんですよ。料理の形をしてない。シチューか泥かみたいな料理を食べています。
シャンピオンが座っている椅子が天秤になっていて、錘より重いとアラームが鳴って、ご飯は全部犬にあげる。そんなシビアな生活です。昔はブクブクで可愛いかったのが、ガリガリの足で筋肉だけバーンと丸太のように太く誇張されているんです。
急に冒頭でちっちゃかったシャンピオンがいきなり大きくなったから、しばらく観ていないと同一人物か分からない。
ほぼ別人。
昔観た時は、それがめっちゃかわいそうだったんです。こんなことをさせられてって思っていたんですけど、今回観てみたら、孫を喜ばせようとしていたおばあちゃんが、そんな酷いことをするわけないと分かりました。
虐待ではないね。
後の表情があまりにも鬱々しく怖い感じで描かれているんですけど、それも味がある。
おばあちゃんはシャンピオンにツールドフランスで勝たせたい。
その大会で登場するのが、三姉妹のシンガーで、その人たちは、昔ベルヴィルっていう街で人気だったテレビに出ていた歌手で今は三姉妹のおばあちゃん。
シャンピオンを救出する時に、助けてくれるんですよ。
その人たちは今も舞台でに立って暮らしているんです。汚い家に住んでいて、衝撃なのが、近くの池に爆弾を投げ込んでカエルを取って食べるシーンです。家で観ていると食欲が薄れます。
串焼きにします。でも個人的にはデザートの方が衝撃を受けた。
おたまじゃくしをポップコーンのように。
親子を食べてしまうんやね。
あの記憶は鮮明に残っています。
そこはゴキブリがいたり、廊下で恋人同士がいちゃついていたり、歌舞伎町のような場所。
フランスのど真ん中からは、離れていて、ポツンと建った一軒家に住んでいます。
周りの街が豊かになっていって、戦後からの移ろいが家とその周りの風景で表現されています。シャンピオンが大人になった時には家がガクンって傾いているんですよ。そこには鉄道があって、それを通すために家が傾いている描写が入って、電車がどんどん通って、やがて通勤の人がぎゅーぎゅーに乗っている電車が通るようになります。
おばあちゃんはシャンピオンを助けに飼い犬とベルヴィルへ行くんです。
ベルヴィルはアメリカ的で、ニューヨークっぽくて、みんな体が大きくて、ハリウッドをもじって、「HOLLYFOD」って書かれています。自由の女神みたいな像が映って、都会らしさをアメリカ的に描いています。
ベルヴィルってフランス語で「美しい都市」っていう意味らしい。
そうですね、本当にある街らしいです。
チグハグな雰囲気が漂う要素にキャラメイクの不気味さがある気がしますね。
それは最初に言っていた作家の伝統?
同じ監督の「イリュージョニスト(2011)」はそこまでではなかったんですけど、毛色的には同じ感じかな。侘しさは「イリュージョニスト」では感じなかった。
おばあちゃんを除くキャラクターの大半が異様に太っているかガリガリかで、死んだ魚のような目をしてるから暗い印象。
特にシャンピオンはマフィアに攫われても、表情が変わらない。
マフィアが攫った理由も独特。
賭け事の道具に使うために選手3人を連れ去りました。マフィアの建物で自転車を漕がして、疲れて脱落した人は殺されるデスゲームです。誰が生き残るかの賭けをしているのをコミカルに描いています。
あの三姉妹も活躍していたもんね。
おばあちゃんたちがめっちゃ強くて、爆弾を仕込んだ靴を投げて派手に戦っています。
若い時の三姉妹が出ているテレビ映像が、冒頭に映るんですよ。ギタリストやダンサーが出てきて、現実の人がモデルにいるような描き方をしている。
(ジョセフィン・ベイカー、フレッド・アステア、ジャンゴ・ラインハルトらが登場)
あそこだけタッチがカートゥーン調。ペティブーブのタッチ。
面白いのが、テレビの中の映像が実写みたいな景色の絵とか、犬が見てる夢のシーンの風景が実写の映像になったります。
実験的な作品ですね。
カンヌ国際映画祭で特別賞を獲っています。
アカデミー賞でも長編アニメ作品賞と歌曲賞でノミネートされました。
主題歌はキャッチーです。
フランス映画は淡々さがあると私は思っているんです。フランス語の発音かもしれないですけど、タタタッて進む感じ。
分かる気がします。
僕はこの監督の作品一覧を見ていたら、びっくりしたことがあったんですよ。なんだか分かかります。「ジョーカー:フォリ・ア・ドゥ(2024)」の冒頭をこの監督が手がけていました。ルーニー・テューンズっぽいアニメーションです。
知らなかった。
このタッチが映画界でブランド化しているんやね。
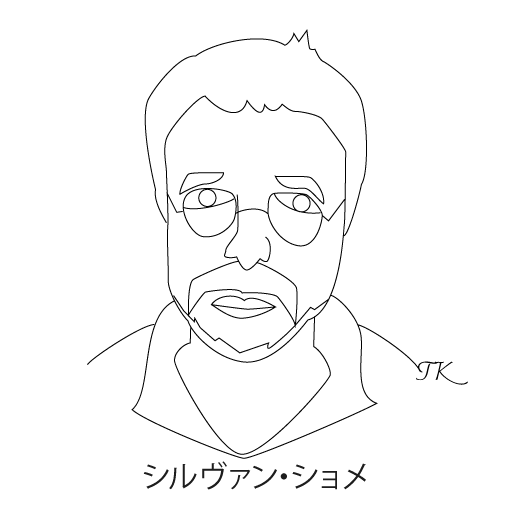
検分役の音楽噺 ♫
今回取り上げられている『ベルヴィル・ランデブー』(02)は僕も大好きな作品で、独特な映像はもとより、ブノワ・シャレストによる音楽がさらに作品の世界観を広げています。
劇伴だけでなく、主題歌、挿入歌、さらに彼自身がエルヴィス・プレスリーばりのヴォーカルを聴かせたりと、音楽面でも楽しめるので、ぜひ機会があれば観て聴いて楽しんでいただきたい逸品です。
さて、本文でも触れられている「バンド・デシネ」という言葉。
世界三大コミックの一つといわれていて、一つはアメリカン・コミック、もう一つはわが日本のコミック、そして、もう一つはフランス語圏のバンド・デシネとなります。
バンド・デシネを代表する作家としては、メビウス(本名ジャン・アンリ・ガストン・ジロー)が挙げられます。
メビウスはコミックの世界だけでなく、映画界でも大活躍していて『エイリアン』、『ブレードランナー』、『トロン』といった作品で彼のデザインが作品に独特のイメージを与えています。
82年の『トロン』は今年シリーズ3作目『トロン:アレス』が公開されましたが、本編では1作目のデザインや音楽も使われていてとても感動しました。
ちなみに『トロン』の音楽は『時計じかけのオレンジ』、『シャイニング』のウェンディ・カーロス、2作目の『トロン:レガシー』(10)の音楽はダフトパンク、『トロン:アレス』の音楽はナイン・インチ・ネイルズが担当。
それぞれの時代の最先端ミュージシャンが劇伴を担当していました。
また、同じくフランスの映像作家ルネ・ラルーの作品にも協力し、『時の支配者』(82)でもデザインに全面協力しています。
今年、ルネ・ラルーの作品『ファンタスティック・プラネット』、『時の支配者』、『ガンダーラ』と三つのアニメーション作品が特集上映されて、耳にされた方も多いと思います。
ルネ・ラルー作品の音楽も魅力的で、特に『時の支配者』の音楽(ピエール・ターディ&クリスチャン・ザネシー)が好きなのですが、未だにCD化もされず、82年にフランス本国でレコードが出たのみでした。
サントラ・コレクターの僕としてはどうしても入手したくて、あらゆる情報網をあたった結果、念願のLPレコードを入手することができました(しかも、前の所有者のフランス語での落書きが残っていました)。
あらら、今回はバンド・デシネから、サントラ・コレクターの話になってしまいましたね(笑)

ベルヴィル・ランデブー オリジナル・サウンドトラック
(対話月日:2025年2月13日)